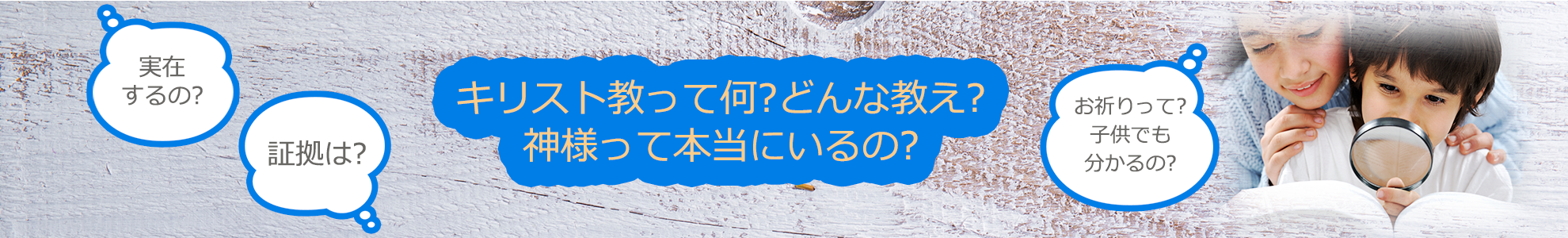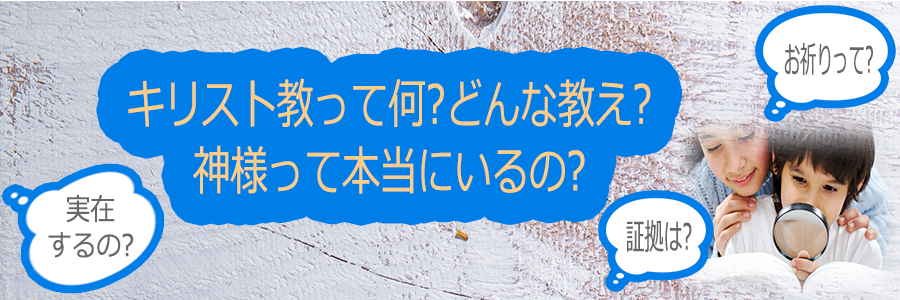
補遺1 放蕩息子の譬が示す人生の三類型
はじめに
これまでみなさんがたに、聖書の基礎的教えを理論的に体系化した教理について学んでいただいたわけですが、これはいわば、聖書全体の骨格のようなものですので、なかにはいささか固い感じを受けた方があったかもしれません。
しかし聖書自体は、哲学書や思想書などのように、実際はそんなにむずかしい説き方をしているわけではありません。むしろ例話や物語などによって、とてもわかりやすく説いています。
もちろん教えそのものは、平易でわかりやすいとはいえ、内容は神の真理なのですから、底知れない深い意味をもっています。ことにも、神と人間の関係について、真に驚くべき事実が啓示されているのです。
その一つが、有名な放蕩息子の譬えと称される物語です。それをこれから皆さん方にも、ご一緒に学んでいただくことにしたいと思います。
これはイエスさまがお語りになった譬え話ですが、これはルカによる福音書15章の11節から24節にしるされています。
「ある人に、ふたりのむすこがあった。ところが、弟が父親に言った、『父よ、あなたの財産のうちでわたしがいただく分をください』。そこで、父はその身代をふたりに分けてやった。それから幾日もたたないうちに、弟は自分のものを全部とりまとめて遠い所へ行き、そこで放蕩に身を持ちくずして財産を使い果たした。何もかも浪費してしまつたのち、その地方にひどいききんが遭ったので、彼は食べることにも窮しはじめた。そこで、その地方のある住民のところに行って身を寄せたところが、その人は彼を畑にやって豚を飼わせた。彼は、豚の食べるいなご豆で腹を満たしたいと思うほどであったが、何もくれる人はなかった。そこで彼は本心に立ちかえって言った、『父のところには食物のあり余っている雇人が大ぜいいるのに、わたしはここで飢えて死のうとしている。立って、父のところへ帰って、こう言おう、父よ、わたしは天に対しても、あなたにむかっても、罪を犯しました。もう、あなたのむすこと呼ばれる資格はありません。どうぞ雇人のひとり同様ににしてください』そこで立って、父のところへ出かけた。まだ遠く離れていたのに、父は彼をみとめ、哀れに思って走り寄り、その首をだいて接吻した。むすこは父に言った、『父よ、わたしは天に対してもあなたにむかっても、罪を犯しました。もうあなたのむすこと呼ばれる資格はありません』
しかし父は僕たちに言いつけた、『さあ、早く、最上の着物を出してきてこの子に着せ、指輪を手にはめ、はきものを足にはかせなさい。また、肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて楽しもうではないか。このむすこが死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから』。それから祝宴がはじまった」
この譬え話は、それ自体なにもむずかしいことはない。子どもにもわかるとても平易なお話しです。ですから、事改めて解説するまでもないという感じさえします。
しかしながら、実をいうとイエスは、これを子どもたちに向かって話されたのではなく、大人の人たちを対象に語られたお話であったのです。ですから、これはどこまでも譬えとしてのお話であって、この物語のなかには、信仰的・霊的意味が含まれているのです。すなわちこれは、神と人との関係をたとえたものであり、しかも、この神の前におけるわれわれ人間は、いまどのような状態にあるかを図示しているともいえます。
とくにこの譬え話は、皆さんがこれまで学んでこられた聖書の教理、いわば創世記から黙示録まで全部の要点をひとまとめにして、わかりやすくドラマ化した物語であるといってもよいかと思います。
以上のことを念頭において、この譬え話を学ぶなら、わたしどもは神と人との関係について、驚くべき事実を知ることによって、われわれの人生を根本的に考え直す必要に迫られることにもなりましょう。
この譬え話が意味するもの
では、もう一度、この譬え話自体に目を向けて見たいと思います。
この息子は、父の家にいるかぎり、何不自由なく、豊かな生活を楽しむことが出来たはずです。しかし彼は、わがままなところがあり、お父さんと一緒の生活は窮屈で飽き足らなく思っていたようです。彼はもっと羽を伸ばして自由な生活をしてみたいと思ったのでしょう。
そこで彼は、父に財産の分け前を要求し、父の元を去って遠国に旅立ったのでした。すると悪友たちが集まってきて、共に遊び暮らしているうちに、たちまち財産を使い果たしてしまいました。ところがそのとき、運悪く飢饉に見舞われます。そのため生活に窮した彼は、田舎にくだっていって農家に身を寄せ、豚飼いの仕事をさせてもらったのですが、満足な報酬が得られず、飢えて死なんばかりの状態となりました。
ここにきて、やっと彼は正気にかえります。どっちみちこのままでは、野垂れ死にすることになる。命を長らえるためには、家に帰る以外に方法がないと考えます。
こうして彼は、しかたなく故郷に向かったのですが、ようやく家の近くまでたどりついたものの、そこで思わず立ち止まってしまいます。こんな乞食同然の姿では、もう父の子と呼ばれる資格はない。そればかりか、莫大な借金までこしらえてしまった以上、いくらなんでも、もう家に迎え入れてはもらえないだろうとも思います。
ところが、父はどうでしょうか。息子の帰りを待ちわび、いつものように家の門口に立っていた父は、遠くに見えた人影が、帰って来た息子であることをめざとく認め、走りよって行きます。
しかも、弟息子がこれまでの生活で失ったものはもちろん、背負い込んだ借金のことなど、何もかも承知の上で、それを全部引き受けるつもりでいます。
ですから、それには一切触れずに、父は両腕を大きく広げ、抱きかかえるようにして彼を迎えます。そのうえ、乞食姿の彼に、ボロの着物を脱がせて最上の衣を着せ、裸足の彼に靴を履かせ、こうして彼を息子としてわが家に迎え入れてくれたというのです。これはなんという感動的な光景でしょうか。
ところで、この譬え話のなかの父はいうまでもなく天の神を意味しており、放蕩息子は、神に背いて天の父から失われた状態にあるアダム以来のすべての人間を指しています。われわれにとっての父の家はエデンの園です。
われわれ人間はもともと神によって造られ、神によって生かされているものなのです。しかも最初造られたときは完全であったのですから、すべての必要にみたされ、何不自由なく、平和に幸福に暮らしていたのでした。
ところが、その人間がサタンの惑わしにより、神からの自由と独立を求めて、神に背を向け、神から離れて好き勝手な生活をするようになったのでした。父からの自由を求めて家を飛び出したことは、言いかえればそれは、エデンの園からの追放にほかならず、われわれがいま住むこの地上は、いわば神から遠く離れた遠国なのです。
こうして、譬えのなかの遠国に旅立った放蕩息子のように、そこでのわれわれ人間の生き方は、物質万能、経済至上主義、歓楽が目的の消費と散財の生活以外の何ものでもありませんでした。歓楽に浮き身をやつし、放縦と浪費の生活を送ることによって環境破壊や資源の枯渇を招き、世界はいままさに行き詰まりの状態にあるのです。
しかもそれだけではありません。人間はさらに、神に背いてサタンの虜となっているため、これまでたくさんの罪を犯してきています。聖書は罪を負い目と呼んでいます。われわれの罪は、それこそ一生かかっても到底償いきれないほどの莫大な借金を抱えているようなものです。
その結果、われわれの内面的、精神的生活はすっかり荒廃し、乞食同然の状態にまで落ちぶれてしまっているのです。ここにいたって、われわれはやっと、これまでの自分の生き方の誤りに気づき、神に心を向けるようになります。
こうして、われわれが自らの罪を認め、悔い改めて神に帰るなら、そのとき神は、これまでのあやまちと背きの罪をゆるし、ふたたび神の子として迎えてくださるというのです。この譬えはそのことを示しているのです。
しかしながら、神がわれわれ罪人を救うためには、その大前提として罪の処理がどうしても必要です。すなわち、譬えの中で父が息子の着ていたボロを脱がせて最上の衣を着せ、裸足に靴を履かせてくれたように、神はわれわれから、罪に汚れた衣を脱がせ、きよい義の衣をまとわせなければ、神の子として神の家に迎え入れることはできないのです。
そのために、神はどうなさったのか、ということです。罪を聖書は負い目にたとえています。すなわち、罪という借財・負い目、これをキリストは、十字架の死によって、身代わりの刑罰を受け、負い目の償いをすることによって、ことごとくこれを、処理してくださったのです。
さらにその上、最上の衣を着せてくださる。これは十字架の血によって洗い浄められた義の衣です。これによって神は、われらをわが子として神の家に迎え入れてくださるのです。この場合のふるさとは新天新地であり、父の家は永遠の神の都を指し示しています。
ところで、わたしたちはこの放蕩息子の譬えの中に、神から失われた人間の、この世における人生の様々な生き方について、その縮図を見ることができるように思います。
人生の生き方―三類型
まず、この放蕩息子の生涯を、次の三つの段階に区分することできようかと思います。
第一の段階は、彼が父と共なる生活に満足せず、自由を求めて家出をし、遠国に旅立って行き、放蕩に身を持ち崩したことです。
第二の段階は、散財によって無一文となり、飢饉に見舞われることによって、窮乏のどん底に陥り、どうにか豚飼いの仕事にありつけはしたものの、食べるにも窮し、餓死寸前の状態となったことです。
第三段階は、そこでやっと本心に立ち返り、悔いくずおれた気持ちになって、故郷に帰る決心をし、父の家に戻って来たことです。
この放蕩息子の生涯にみられる各段階は、神を離れた人間の生き方の縮図とみることができます。すなわち、神の前における人間の生き方には、次の三つのタイプがあるように思われます。
第一のタイプ
これはいわば、物質主義者とでもいいましょうか。神の存在などまったく念頭になく、徹底した不信・無宗教の生き方に終始します。
このような人は何を目的とし、何に価値を置いて生きているのかと申しますと、それは物的・経済的豊かさです。
その結果、当然のことながら、立身出世・成功繁栄・生存競争による勝利を目指し、経済的豊かさ、世的快楽を追求すること、これを人生の目的とする、いわば徹底的な現実主義者なのです。
このような人は、生まれてから死ぬまでが人生のすべてという現世主義者でもあります。
ところで、このような生き方の問題点は何かといいますと
〝鹿を追う者山を見ず〟
〝金をつかむ者人を見ず〟
という諺のように、人生の視野が狭く、物や金以外は眼中になく、人間にさえも、物や金以上には価値を認めようとはしません。
だがどうでしょう。フランスの思想家パスカルはこう言いました。
「この世(物的世界)の空しさが分からない人は、まさにその人自身が空しいのである」と。
結局、外的・物的世界がすべてという人は、心ここにあらずの自己喪失の人であり、その生き方は、人間不在の人生ということになってしまいます。そして、その人は現世に埋没し、人間性をどこかに置き忘れ、動物とかわらない生き方に満足している人です。
このような人の人生は、結果としてどうなるのでしょう。
つゆとおきつゆと消えぬるわが身かな
浪花のことは夢のまた夢(秀吉)
〝歓楽極まって悲哀生ず〟という言葉もあるように、結局はパスカルが言うように、このような人生もその人も、死をもってすべてが終わり、ついには空の空に帰することになるのではないでしょうか。
第二のタイプ
第二のタイプは、精神主義者とでもいいましょうか。道徳的な生き方こそが人間にふさわしい意義と価値のある生き方であると考える人です。このタイプの人は、物やお金に絶対的な価値をおくことはしません。これを人生の目的とはしないのです。そうしたものに真の満足、生き甲斐、幸福や喜びがあるとは考えないからです。
むしろ、精神的、思想的、道徳や倫理、すなわち人格的なものこそが、人間の本質的なものであるとして、人生の生き方を考えるのです。絶対の価値を物ではなく心に、経済ではなく精神に、快楽ではなく道徳に置く。このように、人生の目的は物や金ではなく精神的なものにあるとし、人間の本質は身体ではなく人格や徳性にあると考える。ゆえに人生の意味目的は、精神の涵養・人格の陶冶、徳性の錬磨・人間の成長、にあるとする。肉体は精神の宿る器にすぎず、物や金は人間が生きるための道具であって、これらはあくまでも精神や人格の従属物にほかならない、のみならず、物や金は人間の欲望を刺激し、紐のように足を絡めてよからぬほうに引っ張って行く。ゆえにこれをむしろ人格的成長向上を阻むものとして、制御し抑圧すべく、道徳修養・難行苦行・忍耐我慢にこれ努める。いわば勤勉型・努力型の人間です。
ただし、この生き方の人はとかく、人間中心、自分本位の考え方に立っており、人間にできないことは何もないとばかりに、何事も解決はすべて自分の意思と努力でというふうに、どこまでも絶対的な自己信頼の態度をつらぬく勤勉努力型の人です。
このような生き方の人は、自己自身にある程度の満足感を与え、誇りと優越感をさえもたらしてくれるでしょう。だがそれは、どこまでも表面的・外形的なものにすぎず、内実はどうかといいますと、心には真の達成感・充実感がなく、歓喜も平安もないということになりかねません。むしろ、魂の空洞化、言い換えれば精神的飢餓状態に陥る人もなくはないでしょう。
このようにみてきますと、この第二のタイプは、人間としてまことに立派で、一見非の打ちどころがないようにもみえます。
ところがこれも、神の言葉である聖書を鏡として、これに照らしてみるならどうでしょう。得てしてそれも偽善的であって、外観や形式を重視するあまり、内側をなおざりにし、外と内とが必ずしも一致しないという現実がまま見受けられがちです。
かつてイエスは、道徳的な面において人々の模範とされていたバリサイ人に向かって、こういわれました。
「偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。あなたがたは、わざわいである。あなたがたは白く塗った墓に似ている。外側は美しくみえるが、内側は死人の骨や、あらゆる不潔なものでいっぱいである。このようにあなたがたも、外側は人に正しく見えるが、内側は偽善と不法とでいっぱいである」(マタイによる福音書23:27、28)
このように、道徳主義は外側は白く美しく見えても、内側は骨や灰とは言わないまでも、命のない形骸だけになりやすいという傾向があります。ですから、ラ・ロシュフーコーがいっています。
「人間の美徳は、つねに仮装した悪徳にすぎない」と。
このタイプの人は、人間中心、人間本位の考え方に立ち、人間にできないことは何もない、すべて解決は自分の手で、といった強い自己信頼がみられます。このような生き方は、ある程度自我を満足させ、誇りと優越感をいだかせもするでしょう。だが、ある哲学者がいっています。
「道徳は常に変化している」。
一見不変と思われる道徳観念も、時代により、民族により、しかも自他の間でさえ、相違があり、また変化もみられます。としたら、これがはたして人生を生きるための絶対的な価値基準となりうるものでしょうか。
思想家ジューベールもいっています。
「体とおなじように精神も脱臼することがある」。
かつて、大和魂を、世界に誇りうる、すぐれた精神の基軸と自負していたわが日本も、敗戦によって、その精神も道徳観も突如脱臼したかのように、まったく機能不全に陥ってしまいました。
もちろん、このタイプの人のなかには、このたびの地震災害また原発の被災者たちに示した、支援や献身的奉仕活動にみられるように、偽善などとはとんでもない、愛と犠牲の生き方において、実に模範的な方々が少なくないのも事実でしょう。
けれども、そうした人間の犠牲や奉仕には、やはり限界があることもまた否定できない事実ではないでしょうか。人間には、常にそうした限界性というものが伴うものであるかぎり、善意は善意として認め、尊ぶとしても、やはりそうした人々にも、ほかにもっと大事な何かがあるように思うのですがどうでしょうか。
そして、それを持たないかぎり、その人もいずれは、飢えて死ぬばかりの状態になったあの放蕩息子のように、精神的霊的飢餓状態に追い込まれるときがくることになりはしないでしょうか。
結局のところ道徳主義者は、「武士は食わねど高楊枝」で、外側はどんなに見栄を張ってみても、いずれは精神的飢えに迫られるときがくるのです。
これについての象徴的なできごととして思い起こされるのは、戦時中、闇米を法律違反として買おうとしなかったため、飢えて死んだといわれる裁判官山口判事のことです。
人間的には立派にみえるこの第二のタイプの人は、かなり程度人間としての誇りをもっており、それだけにまた、自己満足に陥っているようにも見受けられます。
それにもかかわらず、こうした人々の多くは、肝心な何かが欠けているように思われるのです。それはいったいなんでしょうか。
それはちょうど、家を離れて遠く旅立った弟息子のように、神の存在を認めず、その必要を感じていないということです。宗教にはまったく無関心で、信仰というものを、弱者には必要であっても自分には必要のないものとして、これを軽視しがちです。そればかりか軽蔑しさえします。
このような精神主義者・道徳論者は、結局のところ、ついには人生に行き詰まり、餓死寸前の状態に追い込まれることにもなりかねないでありましょう。
それでありながら、この人にとってはやはり、現世がすべてであって、人生とは生まれてから死ぬまでのあいただけのことと割り切っています。来世については依然としてまったく考えようとはしないのです。
このような人間のありさまについて、旧約の預言者イザヤは次のように描写し、指摘しています。
天よ、聞け、地よ、耳を傾けよ、
主が次のように語られたから、
「わたしは子を養い育てた、
しかし彼らはわたしにそむいた。
牛はその飼い主を知り、
ろばはその主人のまぐさおけを知る。
しかしイスラエルは知らず、
わが民は悟らない」
ああ、罪深い国びと、不義を負う民、
悪をなす者のすえ、堕落せる子らよ。
彼らは主を捨て、
イスラエルの聖者をあなどり、
これをうとんじ遠ざかった。
あなたがたは、どうして重ね重ねそむいて、
なおも打たれようとするのか。
その頭はことごとく病み、
その心は全く弱りはてている。
足の裏から頭まで、
完全なところがなく、
傷と打ち傷とと生傷ばかりだ。
これを絞り出すものなく、包むものなく、
油をもってやわらげるものもない」(イザヤ書1:2-6)
これはまさに、神に背き、神から失われた状態にあるわれわれの姿、そのままではないでしょうか。そして、これが神の前におけるわれわれの姿であるとしたら、それはなんと惨めな哀れな姿であることでしょう。しかも、これこそが、第二のタイプの人の生き方であるのです。
第三のタイプ
第三のタイプの人というのは、宗教の世界に目の開かれた人ということになりましょうか。人生の空しさ儚さを悟り、自分の無力さと頼りなさに気づきます。その結果、自分を超えた絶対者の存在を認め、これによりすがる以外に生きる術がないと思い定めた人です。
譬えの中の放蕩息子で言えば、放蕩のために無一文となり、途方に暮れてそこに立ち止まり、これまでの生き方を反省する。自分には、何かが欠けていると感じ、大事なものを見失っていたことに気づく。それは故郷を捨てたことであり、何よりも父の愛と保護の有り難さを心に止めず、親の恩を仇で返すようにして父に背いていたことです。
これはそのまま、われわれのこれまでの神に対する態度であり、振る舞いであったのです。人生の行き詰まりは、神との関係の破れにあることを知るのです。それと気づいた彼は本心に立ち返り、急に故郷が恋しくなって、父のもとに帰ろうと決心する。これが回心の経験であり、求道の生活のはじまりなのです。
「己の限界に目覚めたとき、人は絶対者の存在を問い始める」(サインズ誌)
こうして彼は、人生の考え方、生き方の間違いを悟り、その結果、人生の方向転換を謀り、魂の故郷に向かうことになる。すなわち人生の軸足をこの世と自己から、神の側に移して、神中心の生き方に転換する。こうして人は、神を認めて自己を見出し、神を信じることで喪失している自己を回復することになるのです。
これまで、神の顔を避け、神に背を向けていたのが、神に顔を向け、神を熱心に尋ね求めるようになる。人生の行き詰まりは神との関係の破れにあったのだから、その行き詰まりの打開は神との関係の修復こそが急務であると悟るのです。
ナポレオンはいっています。
「宗教のない社会は、羅針盤のない船のようなものである。それは航路を確かめることもできないし、港に入港することも望めない」。
ですから、日本の著名な哲学者・西田幾多郎博士はこういうのです。
「学問道徳の本には宗教がなければならぬ。学問道徳の極致は宗教にはいらねばならぬ」
しかも、神学者ラインホルド・ニーバーは、宗教についこう説明しています。
「宗教とは、人生のすべての崇高な価値の探求である」。
もちろん、こうした生き方の問題点としては、次のようなことが挙げられましょう。
「さて、信仰とは、望んでいる事がらを確信し、まだ見ていない事実を確認することである」(ヘブル人への手紙11:1)
「わたしたちは、見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠につづくのである」(コリント人への第二の手紙4:18)
宗教の世界は確かに、物質や経済のように目には見えない。それは精神のように触れたり感じたりもできない、という問題があるにはあります。なぜならそれは超越者が対象だからです。
ですから、われわれの神との関係は、確かに信仰によって認知するほかはない、というのは事実です。したがって、われわれは人生に行き詰まり、自己に絶望しないかぎり、信仰の世界に人生の方向を変えるということは、簡単にはできないし、容易にその気になれないということがありましょう。
しかしながら、もしわれわれが人生の儚さを知り、人間の限界を思い知らされ、真実なるもの、永遠なるものを得たいと思うならば、神を信じてこの道を進む以外にはないはずなのです。
「狭い門からはいれ。ほろびにいたる門は大きく、その道は広い。そして、そこからはいって行く者が多い。命にいたる門は狭く、その道は細い。そして、それを見いだす者が少ない」(マタイによる福音書7:13、14)
だがその結果はどうでしょう。
神は、われわれのこれまでの背きを赦し、神の子として迎えてくださる。これが第三のタイプの生き方です。それはいわば信仰の生活・宗教的人生ということになります。
ではここで、もう一度要点を整理してみましょう。
第一のタイプは、物的・快楽的人生観の人
これは、外側の環境に頼る生き方であり、いわば地面だけを見て歩む動物的生き方です。
第二のタイプは、精神的・道徳的人生観の人
これは、理想主義的・人道的ですが、自己信頼の人であり、いわば人間本位の生き方です。
第三のタイプは、霊的・宗教的人生観の人
これは、神に頼る生き方であり、いわば天的生き方の人ということができましょう。
いったい、こうした生き方の結末は、それぞれどのようなことになるのでしょうか。
わたしたちは、聖書の中にその原型を見ることができるように思うのです。
第一のタイプは、ノアの洪水型
このような生き方は、ノアの時代に見られた光景によく似ています。
神はこういわれました。
「わたしの霊はながく人の中にとどまらない。彼は肉にすぎないのだ」
「主は人の悪が地にはびこり、すべてその心に思いはかることが、いつも悪いことばかりであった。主は地の上に人を造ったことを悔いて、心を痛め「わたしが創造した人を地のおもてからぬぐい去ろう」(創世記6:3、5-7)
最初のタイプの生き方は、ノアの時代、神の警告を無視し、神の招きに従わなかったため、世界的洪水で地上からぬぐい去られたあの人々に、その原型を見ることができるように思われます。
第二のタイプは、バベルの塔型
このような生き方は、喩えていえば、バベルの塔を築こうとした人々のようなものだといえないでしょうか。人間の知恵知識、技術文化等によって、人間的野心をほしいままにし、時には、かがやかしい栄誉を手にすることもありえましょう。しかし、そのバベルの塔は、実は崩壊寸前の状態にあり、その結果、当然のことながら、ついには挫折を避けることができない定めにあるということを知る必要があります。
第三のタイプは、ヤコブの夢型
このような生き方は、むかし家を飛び出したヤコブが、飢えと疲れのために、死んだようになって路傍に倒れ伏し、石を枕に寝ていた。そのとき、彼は夢の中で、枕もとから天まで届く梯子がかけられており、その上を天使が忙しく上り下りしている光景を示されました。そして、夢から醒めた彼は叫んでもうしました。
「『まことに主がこの所におられるのに、わたしは知らなかった』。そして彼は恐れて言った、『これはなんという恐るべき所だろう。これは神の家である。これは天の門だ』」(創世記28:10-17)
このヤコブの見せられた夢にこそ、第三のタイプが示す生き方の原型をみることができるように思うのです。
むすび
さて、イエスのお語りになったこの放蕩息子の譬え話、これは何を意味し、どういうことをわたしどもに訴えようとしているのか、おわかりになったでしょうか。
この譬えの中の父親は、天の神様をさしています。息子はもちろんわたしども人間のことを喩えています。
聖書によれば、わたしども人間は神によって造られ、また生かされているのです。しかも、最初造られたときには、神と共にあって何不自由のない、平和で祝福に満ちた生活を送っていたのでした。
ところが人間は、サタンの惑わしにより、神からの自由と開放を求めるようになりました。その結果、神の支配の外に迷い出てしまったのです。こうして人間はいま、神から失われた存在となっています。
この世界の災害や混乱、また人間の苦難や不幸は、その結果として生じるようになったのです。
こうして、神を離れた人間は、自分の思うがままの生き方をするようになり、人間の持てる知恵と力を駆使して、文明・文化を築き上げ、物的繁栄を誇りとして、便利で快適な生活をほしいままにしています。
しかし、そうした生き方にも、ついに翳りが生じてきています。科学の進歩は人間の生活環境を破壊し、経済の成長は資源の枯渇をもたらしました。その結果、後進国ではいま、何十万という人が飢餓状態にあって苦しんでいます。否、文明国においても失業者が増大し、生活に窮して自殺する人さえ出始めているというありさまです。こうして世界の前途は、まさに完全な行き詰まりの状態にあるのです。
ここにきて、人々はこれまでの生き方について,疑問を感じはじめているように見受けられます。どこに間違いがあったのか。何が欠けていたのか、と考えるようにもなってまいりました。
しかし、本心に立ち返るところまでは、まだ行っていません。残念ながら殆どの人は、故郷を忘れています。父の家をおぼえていません。神の存在など考えてみようともしないのです。そのため魂は、精神的・霊的飢餓のため、まさに瀕死の状態におかれているありさまです。
イエスの譬え話の中の放蕩息子は、そのとき本心に立ち返ったとあります。そして彼はこう決心したというのです。
「『父のところには食物のありあまっている雇人が大ぜいいるのに、わたしはここで飢えて死のうとしている。立って、父のところへ帰って、こう言おう、父よ、わたしは天に対しても、あなたにむかっても、罪を犯しました。もう、あなたのむすこと呼ばれる資格はありません。どうぞ、雇人のひとり同様にしてください』そこで立って、父のところへ出かけた」(ルカによる福音書15:18-20)
放蕩息子は、ここでこれまでの生き方の誤りを、はっきりと認めました。そして徹底的にへりくだり、心からの悔い改めを行ったのです。その結果、彼は父のところへ出かけたとありますが、これがわれわれの場合、求道入信の生活を意味します。
ところで、その結果はどうであったでしょうか。本来なら、地上の父の場合、「なんだと、いまごろになって帰ってきたというのか。とんでもない。あの出ていったときのことを考えたら、いまさら、この家の敷居を跨げる身でもあるまいに」と、戸を開けてはくれず、世間体が悪いとばかりに、追い返されるのがおち、というところかもしれません。
しかし、天の父はそうはしませんでした。それどころか、われらがこれまでの生き方の誤りを認め、悔い改めて神に帰ってくるのを待ちわびておいでになるということなのです。
ヤコブよ、イスラエルよ、これらの事を心にとめよ。
あなたはわがしもべだから、
わたしはあなたを造った、
あなたはわがしもべだ。
イスラエルよ、わたしはあなたを忘れない。
わたしはあなたのとがを雲のように吹き払い、
あなたの罪を霧のように消した。
わたしに立ち返れ、
わたしはあなたをあがなったから。(イザヤ書44:21、22)
こうして神は、われらを喜び迎えてくださるのです。
このイエスの譬え話の中には、以上のような意味がこめられており、それがこんにちのわれらにも告げ示されているのです。この短い物語の中には、神の救いの計画の全貌が、余すところなく描き尽くされています。
それにしても、この分かりやすい単純な物語のなかに、神と人間との関係について、そしてまた人間が神の前に、いまどのような状態にあるのかということについて、まるでドラマでも見るように、いきいきとしかも具体的に開示されていることは、なんという驚きでしょう。
その上、神はわれらのために救いの手立てを構じ、われらが悔い改めて神に立ち帰るのを待ちわびておいでになるというのです。
何もかもが行き詰まりの状態にあるこの地球上において、まったくの絶望状態にあるわれら人類にとって、これはなんという希望と慰めにみちた幸いなおとずれではないでしょうか。
では、どうしたらそのような神の救いに与ることが出来るのか、その条件や具体的方法については、下巻に詳しく説明していますので、併せてそれをもお学びくださるようおすすめいたします。
賛美歌517番
「われに来よ」と主は今 やさしく呼びたもう。
などて愛のひかりを 避けてさまよう。
「帰れや、わが家に帰れや」
と主は今呼びたもう。
疲れ果てし旅人 重荷をおろして、
きたりいこえ、わが主の愛のみもとに。
まよう子らのかえるを 主はいま待ちたもう、
罪も咎もあるまま きたりひれふせ。